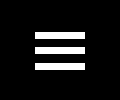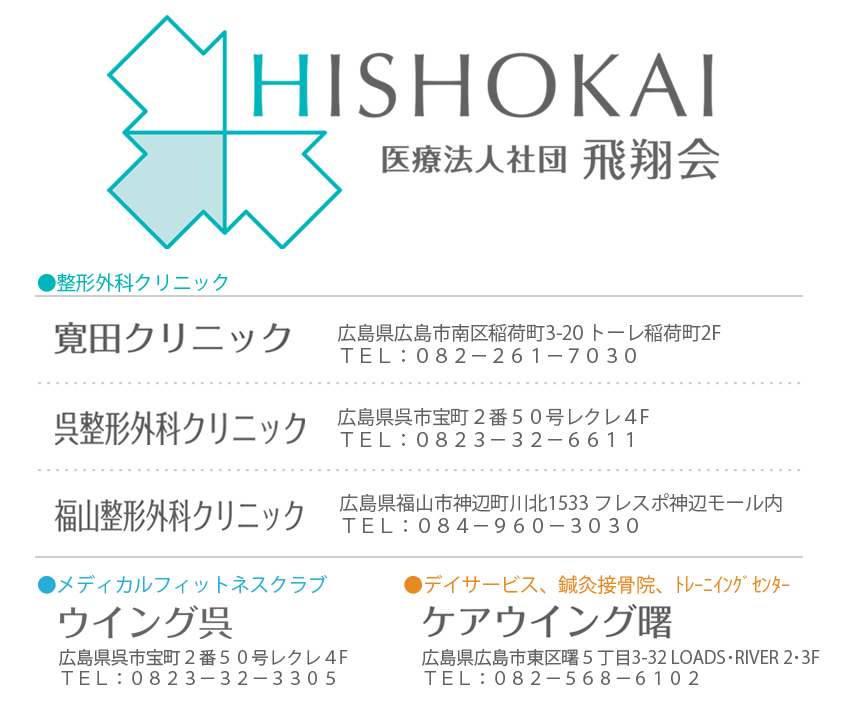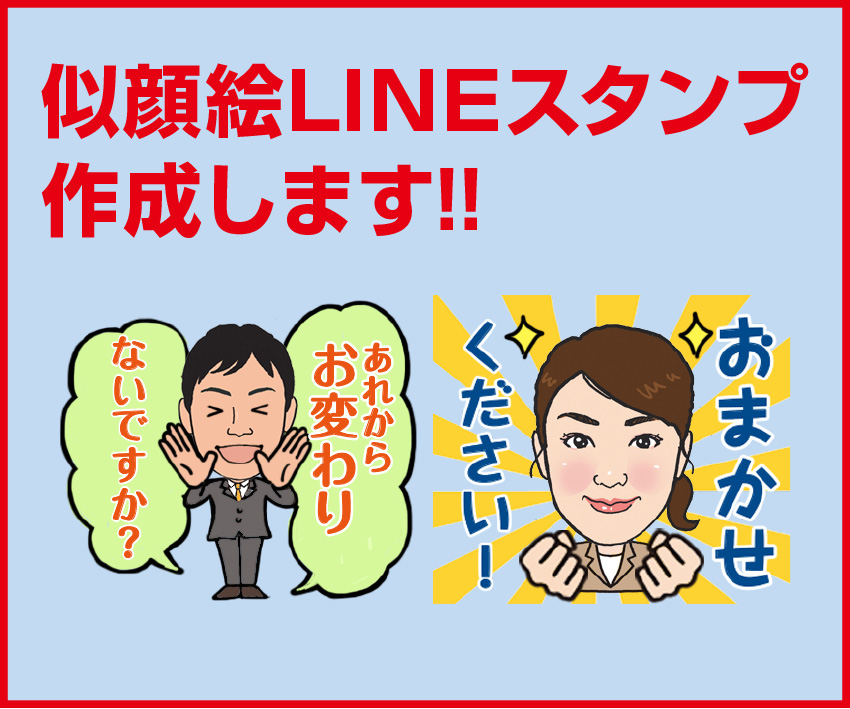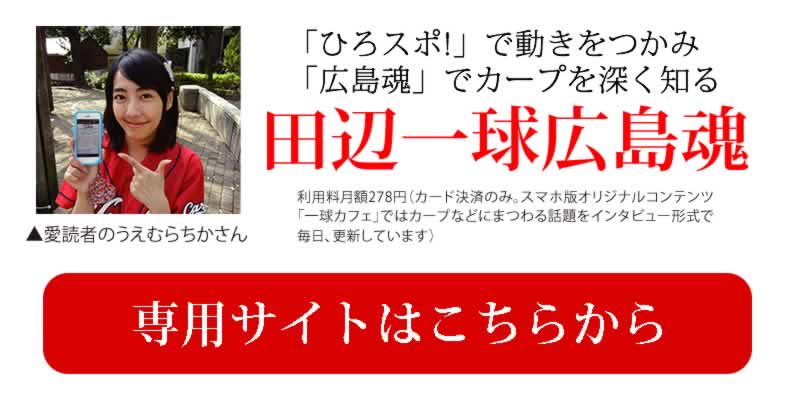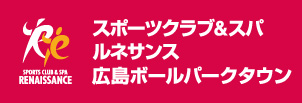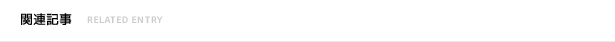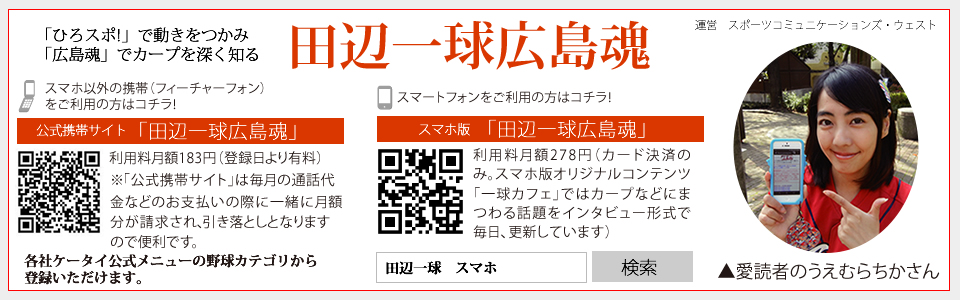榎川は車道に沿って住宅地を流れているためいくつもの橋が架けられている、その橋のひとつにひっかかって止まった巨大な円球型の岩。この巨大な物体がおよそ2キロ上流からゴロゴロと転がってきたことになる…(トップ画像)
報道する側はこの非常時においては「ストーリー性より情報を!」
豪雨災害発生から一週間。7月13日のテレビ朝日「ワイド!スクランブル」の中で男性コメンテーターが強い口調で語っていた。
まったく、その通りだ。
大災害の際の優先順位をマスメディアが間違えては話にならない。
もっと言えば広島の放送メディアは被災発生時に生枠で通常のバラエティ番組などを流していた。テレビ画面に文字情報を流すタイミングも、局によって大きな差が生じていた。
被災地で、わらにもすがる思いでラジオのスイッチを入れたら「くだらないレギュラー番組の男性の声」(被災地の声)では何のための地元密着メディアか、ということになる。
インフラ、交通、人とモノの流れ、被災地の「今」と被災地として認識されてもいない地域の堀起こし。
2014年8月、広島市で分かっているだけでも77名もの死者を出した大規模土砂災害でも、ずいぶんあとになってから、いろいろな行政サイドの不手際や支援策のいたらない部分が深堀される報道がなされた。
もう反省や課題はかなりの部分で関係者の間では把握されている。今回のケースはなおさらだ。
早くから尋常ではない大雨が降ることは行政側、防災担当者も市町の首長も分かっていたのである。
例えば雨が上がって3日後に起こった広島県安芸郡府中町の榎川氾濫による泥流災害。
もし雨上がりを待ってすぐに県や町の担当者が川の上流に向かい、その目で、あるいはドローンによる空撮を駆使して、現場一帯を広く確認したならば、もしかしたら川の氾濫は防げたかもしれない。
規模が大きすぎてそれはとても無理だったとしても、2万5000人への避難勧告を出すよりも前に、下流域に土嚢を積み上げるなどの対策は十分にできた。
サンフレッチェ広島の城福浩監督は今回、募金活動などを通じて大災害と向き合う際に、次のような言葉を残している。
「我々は県民の方々に支えられています。こういう苦しい時にできることがあれば、ピッチ外でもやっていきたい。試合前なので選手のコンディション的には試合に照準を合わせたいところですが、それより大切なことがあります」
「我々の存在意義を考えさせられるような毎日です。じゃあ自分たちに何ができるか、何をしなければならないか、を研ぎしましていかないといけない」
「こうした活動を通して選手もひとつになれる。みなさんから、応援しています、一緒にがんばりましょう、と声をかけていただきました。改めてモチベーションが上がってきました。災害に遭われたで苦しんでいる方、そんな中で努力されている方たちの力になれるよう、広島県民のみなさんと一丸となって戦いたいと思います」
城福浩監督の言葉を借りるなら「自分たちに何ができるか、何をしなければならないか、を研ぎしましていかないといけない」ということになる。
それはその地域に住むひとり、ひとりもだし、住民の財産や生命を預かる立場の側であればなおさらである。
一度に50人以上が亡くなった倉敷市真備町の事例など、自然災害としてだけ片づけられるはずもない。あとになって検証すればその不手際、イコール人災の部分が浮き彫りになる。府県別で最多の死傷者を出している広島では今後、そのひとつひとつの事案に対して徹底した調査・検証が行われる必要がある。
今回よりさらに大規模な災害に見舞われる前に…
広島スポーツ100年取材班、ひろスタ!特命取材班
以下、榎川が氾濫した翌日の7月11日早朝に撮影した榎川上流、水分峡(みくまりきょう)と呼ばれている林道入り口までの状況を紹介する。

榎川の川幅が広くなり、流れも緩やかになる「えの宮公園」前、バス通りから上流を望む。重機のある先に泥流を堰き止めた寺山橋があり、この画像の左側、川土手より低い場所は広範囲にわたって泥水に覆われた。

上の画像より下流、そばの府中町立府中中学校が避難所になったが、ここも川土手より相当低い位置にある

榎川に沿って上っていく

川土手の西側地区は大変な状況



この記事のアイキャッチに使った巨大円球型岩が橋脚で止まっている様子を上流側から望む

榎川沿いの民家に残る泥の跡

上の画像の民家の目の前にあるこの橋は一躍、全国区になった。突如として木々を含んだ泥流がこの橋にものすごい勢いでぶつかる映像が各局によって報じられた。この橋には橋脚がない。よって前出の巨大円球型岩はここも通過したことになる。想像しただけで恐ろしい…

榎川沿いに急な坂を上っていくと、やがて住宅が少なくなり川幅も狭く川底も浅くなっていく。この画像で注目すべきは、中央に見える木の枝葉に泥がついていることだ。この高さまでの泥流がここから加速していったことになる、次の画像はこの場所を上流側から見たもの、やはり枝葉に泥がついている。

そしてここから先、上流になるに従い川岸の被害が顕著になる

ズタズタボロボロ…車道は完全に崩れ落ち通行止め、次の画像はこの場所を上流から見たもの


上流に進むと削り取られた爪痕はさらに大きくなる

砂防ダムのある水分峡まで残り数100メートルの地点、むき出しの各種ライフラインがやばい…

上流側から見ると、流れが左にカーブするところで河岸が破壊されていることがわかる、巨大な流れによるエネルギーをまともに受けたことになる

砂防事業完成図紹介看板、がむなしい…砂防事業でここら界隈はおそらく万全の態勢!となったのだろうが、人間の考えることの遥か上を行く、それが自然災害、だ。

流れが直線になっているところは川から泥流が溢れなかった模様、河岸の花壇の花にも何の被害も出ていない。ここをすさまじい泥流が下っていき、加速した様が容易に想像できる…

川のそばには大規模な墓苑もある
公園内を進んでいくと最初の砂防ダムがある。砂防ダムは7か所も整備されている。

最初の砂防ダム。雨が上がって3日以上が経過してもこれだけの水量…「時差災害」が起こるのは当然で、未然の減災策はいくらでもあったはずだ

上の画像では平常時は堰堤から数メートル下にある川底がいっぱい、いっぱいのこころまできている。このため上流からの巨大な流れをここで一度、水平方向から垂直方向のエネルギーに換えることはできても、下流域の被害を防止する本来の「運搬土砂量調整」の役割を果たすことはもうできない。
さらに上の画像…
堰堤の途中まで泥がこびりついている。その高さは「水通し幅」がとってある堰堤の低い部分よりずいぶん上の方まできている。
ということは一時期、その泥のついた位置まで木々や岩混じりの泥流が来て、そこで運よく、堰き止められ、後ろからの圧力によってついに”決壊”したとも考えられる。
あるいはこの上流から莫大な量の土砂がイッキに押し寄せ、あっという間に「水通し幅」に達して残りが全部、巨大な位置エネルギーと化して下流域に押し寄せたのか?
もちろんこれは素人考えに過ぎず、専門家の検証を待つことになるが、次に大雨に見舞われれば、また同じことが起こる可能性があるのでは?ぐらいのことはド素人でも分かる。

自然のダムの役目を果たすはずの山肌から、晴天続きでも水が溢れ出している
![HIROSHIMA SPORT HIROSPO [ひろスポ!]](https://hirospo.com/wp-content/themes/hirospo/img/common/logo.jpg)
![HIROSHIMA SPORT HIROSPO [ひろスポ!]](https://hirospo.com/wp-content/themes/hirospo/img/common/sp_logo.gif)