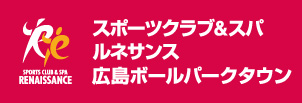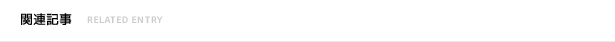2000年10月10日に開始以来、カープ情報を発信し続ける有料携帯サイト「田辺一球広島魂」(通常携帯・ガラケーではドコモ、au、ソフトバンク公式サイト)がとうとう16年目に突入した。
スタート時には中国放送の「RCC広島カープ」公式サイトがプラットホームとなっていた。以来、形を変えながら一日も休むことなくカープとカープナインの情報を発信し続け2016年10月10日をもって17年目に突入した。
人気のコンテンツは黒田、新井貴浩らカープナインの素顔に迫る「コラム赤の魂」、全国のカープファンが自由に「声」を出し合い熱く討論する「コイの季節をあなたにも」、独自の切り口で「実況」する「試合速報」、「ファーム情報」など。
逆に言えば16年間に渡り一日も欠かさず愛読している読者が多数存在するということにもなり、「書く方」も「読む方」もギネスもの!?である。
携帯サイト「田辺一球広島魂」アクセスはこちら!
スマホ版ikkyuu-t.com
通常携帯版 www.ikkyuu-t.info/i
2016年9月15日コラム「赤の魂」より「赤ヘルの街2016未来の君たちへ」
赤い景色が大きく揺れて、その瞬間がやってきた。
CENTRAL LEAGUE CHAMPIONS
ずっと、届かないものと思っていた、チャンピオンフラッグがマツダスタジアムを埋め尽くすファンの前に広げられた。
スタンド側先頭に緒方監督、続いて小窪選手会長、菊池、田中、鈴木誠也。もう一方には前から丸、野村、今村、中崎…。天然芝の緑のグラウンドに初めてもたらされた王者の印。詰めかけたファンの目に、テレビ中継を通して見守る人々の目に、その様子はどんな風に映っただろうか?
「本当に優勝したんですね…」
1975年10月15日に初優勝を果たした当時の古葉竹識監督が10月19日、旧広島市民球場でこの夜と同じように地元凱旋を果たした時に残した名ゼリフである。
戦後の混乱期、1950年1月15日に現在の広島県庁がある西練兵場跡でチーム結成披露式。1949年の球界再編、2リーグ制への移行を機に広島に誕生した新球団。すべてが焼き尽くされ、破壊し尽され、屍の街と化してからわずか5年。いやだからこそ、の強烈な思いが当時の関係者を、市民を突き動かした。
そして球団創設から26年目にして栄光の旗をこの街の真ん中に力強く打ち立てた。3年連続最下位の逆境から一気に上り詰めた。赤ヘルと機動力野球、連動する打線と個性派揃いの投手力が夢を現実に変えた。
旧広島市民球場周辺に長らく残っていた原爆によるバラックがすべて姿を消したのも、広島の街を新幹線が走り抜けるようになったのも同じ時期だ。
あの初優勝から41年、前回、旧広島市民球場最後の優勝となった1991年から数えても25年。
やはり歴史は繰り返す。今回のセ・リーグ制覇の「起点」となったのもやはり2004年に勃発した球界再編問題だった。
近鉄球団は瞬く間に消滅の道を辿り、さらなる合併も複数画策されていた。そのころのカープは残念ながら小さな池の底で、じっと嵐の去る時を待っているようなものだった。だが、平成版の球界再編の嵐は強烈で、巨人を中心とした経営者側の都合だけが優先され、ファンや「たかが選手」の存在は二の次となりかけた。
そんな中、全国のプロ野球ファンが巻き返しに転じた。広島では黒田や新井貴浩が中心となって、ファンとチームとの新たな交流策を模索し、やがて赤いストライプのユニホームを着てスタンドにやってくるのが当たり前のような時代へと入っていく。
“静”の姿勢を貫いていた球団も“動”に転じ、遅まきながら組織の中に「地域課」が新設された。カープ坊やなどの商標の使用も手軽にできるようになり、球団と広島の街との”融合”が急速に進んだ。同じころ、空中分解しかけていた「新球場問題」も「貨物ヤード跡地への新設」で決着を見た。
その球界再編騒動からだと12年、みんなが夢にまで見続けてきたチャンピオンフラッグが、ナイター照明に浮かび上がりグラウンドを一周する。
その後方を歩く新井貴浩は笑顔でスタンドのファンの声援に応え、そしてそのさらに後ろで背番号15はひとり、何ごとか考えるような表情で赤いスタンドを見上げている。
思えば黒田広島にやってきてからでももう20年、もっと言えば黒田が生まれたのが1975年2月10日…
彼の人生を借りるようで恐縮だが、カープ7度の優勝の歴史に照らし合わせるとその41年間はまるまる重なっていることになる。
当然のことながらその間に幾多のカープファンの人生は終わりを告げ、また新たな命が誕生して赤ヘルの街で成長し、かつての新井貴浩のように親に手を引かれてスタンドへ向かうようになる。
ゆっくりと時間をかけ一周し終えたチャンピオンフラッグと、カープナインの笑顔と、ファンの歓声と。
赤い帽子をかぶったこどもたちがやがてまた大人になり、この日のことを自分の子に伝え、そうやって、またこの特別な赤い風景は、滲む残像とともに、未来へと続いていく。
いつしか球団創設当時の思い出や初優勝の感動が記憶から記録へと移し替えられる時が来ても、誇るべき財産としてずっと語り継がれていく。
![HIROSHIMA SPORT HIROSPO [ひろスポ!]](https://hirospo.com/wp-content/themes/hirospo/img/common/logo.jpg)
![HIROSHIMA SPORT HIROSPO [ひろスポ!]](https://hirospo.com/wp-content/themes/hirospo/img/common/sp_logo.gif)
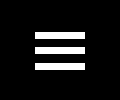




 2016年09月25日
2016年09月25日 2016年09月10日
2016年09月10日