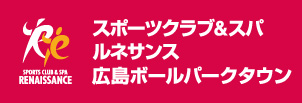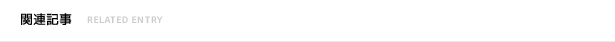元日に開幕した 第90回天皇杯全日本総合バスケットボール選手権大会(オールジャパン2015)が1月12日に決勝を迎える。
広島が立て続けに挑む”東京の壁”
準決勝でトヨタ自動車アルバルク東京を倒した広島ドラゴンフライズにとっては、2試合続けて首都東京のチームが相手となる。しかも「トヨタ」に続いて「日立」…。
広島対東京、あるいはメーン企業スポンサーなしで地場企業からの協賛金と入場料収入で戦うドラゴンフライズ対「世界企業」の「日立」…。
広島の地場企業”だけ”で「世界のトヨタ」を倒したことは、まだチームの様子をよく知らない全国のバスケットボールファに驚きの声とともに受けとめられた。
”トヨタ”に続く強敵”日立”
決勝の相手、日立サンロッカーズ東京も長い歴史と伝統を持つ。
1935年(昭和10年)に創部された日立本社と、1956年(昭和31年)に誕生した大阪に拠点を置く日立大阪とが統合して2000-2001シーズンより活動を開始したのが日立サンロッカーズ東京だ。
日立本社は全日本総合選手権大会(2005年の第37回大会より名称を競技大会から変更)出場14回、優勝3回、一方の日立大阪は同選手権大会出場24回、優勝3回という輝かしい成績を残している。
広島ドラゴンフライズの佐古賢一ヘッドコーチは準決勝のトヨタ自動車アルバルク東京戦
を前に「相手もルーキーがいるので付け入るスキはある」ときっぱり。ただし想定したゲーム展開は「60点台のゲーム」をすれば勝機がるというものだった。
また「80点以上のゲームになるとトヨタの流になってしまう。ディフェンスを自分たちがしっかりできれば…」とも語っていた。
想定外の死闘を制したトヨタ自動車アルバルク東京戦を糧に…
ところがその目論みは外れ、結果的には80-78という”ギリギリのスコア”で広島ドラゴンフライズがトヨタ自動車アルバルク東京に競り勝った。しかも残り数十秒間は、どちらに勝利の女神が微笑んでもおかしくない状況だった。
この試合、第1ピリオドですでに22-23。80点オーバーペースの入りとなった。
ただ、佐古ヘッドコーチは試合前、「この短期決戦で1試合にかける集中力や、勝負どころ、自分たちがイニシアチブをとらないといけない場面での集中力がいい流れになってきていると思いますね」とも言っていた。NBL初参戦の振興チーム。リーグ戦ではこれまで何度も勝負どころで相手に押し切られてきたが、そのひ弱さが今大会の「一発勝負」の中ではいい「集中力」に変わってきた、というのである。
実際、第2ピリオドに入ると互いに得点ペースが落ちて、スタートからのリードチェンジは10回を超える接戦に突入。けっきょくこの10分間では15-15のタイスコアで前半戦を37-38の1点差で終えることに成功した。
前半の広島ドラゴンフライズのスコアは松田8、竹内7、田中6、平尾5、チャップマン4と誰かひとりに頼らない、理想的な攻撃展開になっていた。広島ドラゴンフライズはあくまで「自分たちのディフェンスをやる」(佐古ヘッドコーチ)ことで勝機を見い出す。
確かに広島ドラゴンフライズ側のミスも目にはついたが、この状況は明らかに相手ベンチの方へ重圧となってのしかかった。第3ピリオドを終えて58-58。1ピリオドあたり20点勝負になっても広島側が怯むようなシーンはなかった。
第4ピリオド、残り5分を切ってスコアは68-66、ここからの戦いで「自分たちがイニシアチブをとらなければいけない場面での集中力」がフルに発揮された。心理的限界を超える力を出すことで「運」をも味方につけた。残り2分少々で平尾がスリーポイントを決めて8点差にしたが残り10秒で1点差まで詰め寄られ、そして逃げ切った。
決勝戦でもキーマンになる竹内公輔
このゲーム、チームで一番長く試合に出ていたのは竹内公輔だった。体調が万全でないため2日間、練習を休みぶっつけ本番で果たすべき役割をまっとうした。

竹内公輔選手(右端)が決勝でもカギを握る(画像はNBLのリーグ戦)
竹内 公輔選手はアイシンシーホース三河で2008年からこの大会で4連覇、翌年に移籍したトヨタ自動車アルバルク東京でもチームを優勝に導き、個人的には5連覇を達成している。
ところで日立サンロッカーズ東京には公輔と双子の弟、竹内譲次がいる。二人は5年ぶり(当時、公輔はアイシン三河)に決勝の舞台で激突する。
日立サンロッカーズ東京はNBL、イースタンカンファレンスでは現在、首位を快走中。相手にとって不足はない。
佐古ヘッドコーチはトヨタ自動車アルバルク東京を倒したあとのインタビューで次のように語っている。
「(準決勝突破は)最後までデフェンスがしっかりやり切った結果だと思います。天下のトヨタさんに挑戦する気持ちで選手がよく戦った。ひとつでも上へ、もうひとつ勝っていい色のメダルを持って帰りたい」
広島ドラゴンフライズは年明け、全国の頂点を決める大きな舞台に立ちチームの歴史をまたひとつ刻む。
![HIROSHIMA SPORT HIROSPO [ひろスポ!]](https://hirospo.com/wp-content/themes/hirospo/img/common/logo.jpg)
![HIROSHIMA SPORT HIROSPO [ひろスポ!]](https://hirospo.com/wp-content/themes/hirospo/img/common/sp_logo.gif)
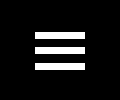




 2015年10月10日
2015年10月10日